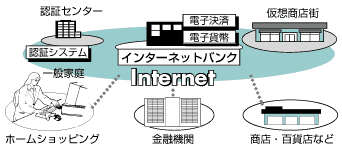Eビジネスという戦略 今日のようにインターネットが広く普及し、IT(情報通信技術)革命という言葉が連日のように報じられると、中小企業の中にはその波に乗り遅れるのではないかという危機意識を持つところが増えているようです。
「Eビジネス」という言葉の正確な定義はありませんが、IT(情報通信技術)を活用した企業活動全般を指し、取引先との電子的な取り引きから、自社内の情報化まで、企業内外のビジネス・プロセスの電子化を指すものと理解して良いでしょう。
そこで今回は、Eビジネスの中のEC(ElectronicCommerce、電子商取引)に焦点を当てて、その情報戦略としての取り組み方を考えてみたいと思います。
EC市場とIT革命 ECは大きく分けて、B to C(企業−消費者間)とB toB(企業間)の2つのタイプに分けられます。前者はインターネット・ショップ(仮想商店)のような形態、後者は生産財の購買取引等の形態を指します。
市場規模はBto Cが1999年は3500億円(対前年比2.1倍)、B to Bが14兆4000億円という統計値が公表されています。これが2005年には、B toCが7兆1289億円、B toBは103兆4000億円になると予想されています。(「平成12年版通信白書」)EC市場規模とその成長率は驚異的であり、もはや無視できるものではないといえるでしょう。
「IT革命」という言葉は、単なる企業の情報化というレベルを超えて、ITが新しい社会ルールや秩序を生み出し、消費者、製造業、流通業、サービス業のすべてのあり方を大きく変化させることを意味しますが、その動きは上記の数値からも読み取ることが出来るでしょう。
今日の低成長経済と成熟市場において、国際的な競争が激化する中で、従来のビジネス・プロセスと組織を見直して、新たな取引先の獲得や、消費者への新たな利便性を提供できる販売方法を追求する動きが高まっています。インターネットの活用は、そうした可能性を模索する企業にとって、時間と空間の制約を超えた新しい手段、ツールを提供してくれるものです。
インターネットショップの取り組み 「2000年版中小企業白書」によると、インターネットショップの開設は平成10年以降急速に増加していますが、その開設目的は表1の通り、「新規顧客との接点獲得」「広告・宣伝」が7割を超えています。また、「24時間受注可能な体制の構築」「顧客の声・要望の収集」という目的をあげている企業が3割あり、「既存店舗への集客増加」「既存顧客とのコミュニケーション強化」という目的が2割前後となっています。
また、表2のようにショップ開設のメリットとして、多数の店舗が「初期投資があまり必要でない」「不動産を借りる必要がない」「多くの従業員を雇う必要がない」「営業をする手間が省ける」ということを挙げており、ECへの取り組みとしてリスク負担が少ないことが特徴となっています。
表3は、やはりインターネットのグローバル性という特性の恩恵を受けて、取引先の80%が「他県」となっていることが注目に値します。
| 表1 インターネットショップの開設理由 |
| 新規顧客との接点獲得 |
72.2 |
| 広告・宣伝 |
71.8 |
| 24時間受注可能な体制の構築 |
33.0 |
| 顧客の声・要望の収集 |
26.5 |
| 既存店舗への集客増加 |
21.8 |
| 既存顧客とのコミュニケーション強化 |
16.2 |
| 経費節減 |
13.5 |
| 従来からの取引業務の電子化 |
6.0 |
| 見込み生産から受注生産等への移行 |
4.6 |
| 需要の予測精度の向上 |
4.4 |
| 取引先からの要望 |
3.4 |
| 自宅勤務者の労働力確保 |
2.9 |
| その他 |
9.1 |
|
| 表2 インターネットショップ開設のメリット |
| 初期投資があまり必要でない |
86.7 |
| 不動産を借りる必要がない |
53.8 |
| 多くの従業員を雇う必要がない |
47.6 |
| 営業をする手間が省ける |
39.9 |
| その他 |
14.0 |
|
| 表3 インターネットショップにおいて比率の高い取引先 |
| 他県の消費者 |
80.0 |
| 地元の消費者 |
13.3 |
| 中小企業 |
1.5 |
| 大企業 |
1.3 |
| 海外の企業 |
0.4 |
| 海外の消費者 |
0.4 |
|
インターネットショップは、既存の店舗をバーチャルな場に移しただけのものではありません。商品を店頭に並べて通行人が飛び込んでくれるのをじっと待っているだけでは、誰も訪問してくれません。そこにはインターネット独自の販売手法が必要となってきます。基本的な考え方として重要なのは、次の通りです。
| (1) |
ショップ・オーナーの熱意と継続的な工夫で、魅力あるショップに作り上げる |
| (2) |
扱う商品は、オリジナル性の高いもの、こだわり商品を前面に出し、他店との差別化を図る |
| (3) |
懸賞付きイベントやバナー広告、電子メール広告の利用、メールマガジンの発行など、積極的なプロモーションを展開する |
| (4) |
アンケート等で見込み客情報を収集し、購買につなげるフォローメール、購買後のアフターフォロー・メールで顧客との関係をつなぎとめる |
| (5) |
顧客と1:1(ワン・トゥ・ワン)で対応し、きめ細かな顧客サービスができるように顧客管理システムを整備する |
| (6) |
初期投資を抑えてショップを開設するため、サイバーモールへの出店、レンタルサーバーの利用などを検討する |
| (7) |
情報更新の方法・体制をきちんと計画する |
| (8) |
訪問販売法第8条に基づく表示、個人情報の扱いを明示し、消費者に安心感を与える(オンライン・マーク、プライバシー・マークの取得など) |
| (9) |
セキュリティを考慮した決済方法、商品配達方法を検討する |
| (10) |
既存顧客からの「口コミ」効果を発揮する公開掲示板等のコミュニティの場を設ける |
インターネットは、リアルタイムで双方向のコミュニケーションを可能とします。したがって、パソコンを使って、多数の顧客に対してきめ細かな情報提供と個別対応をすることができます。デジタルの世界であっても、商売の基本は同じだと心得ましょう。
| 企業−消費者間の電子商取引(BtoC) |
電子決済機関(電子銀行・クレジット会社等)
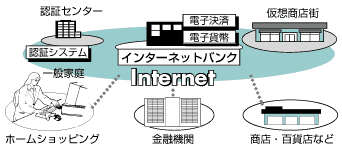 |
現実の商店・商店街との連携 インターネットショップは仮想空間の店舗ですが、実際の出店者は現実に商店を営んでいるところが増えています。「通信販売」の形態は広範囲の顧客を呼びこむ効果がありますが、やはり現実の商店経営にも相乗効果を期待したいものです。
地元の消費者、例えば昼間不在のサラリーマンやOL等の消費者に向けて、特売イベントや新商品情報、割引クーポンなどをアピールして引きつけることも方法でしょう。物品販売でない飲食店などのサービス業は、むしろこうした地元密着型のショップを構築することになるでしょう。
また、地域コミュニティの場でもある商店街が、そのままインターネット上に仮想商店街を構築しようという動きもあります。商業集積による集客効果を、仮想空間においても活用するという考え方です。こうした取り組みを通して、商店街組合の結束力を高めることになり、また個々の商店経営の在り方(品揃え、販促、顧客管理等)を見直すきっかけにもなるというメリットが生まれています。
今回は主にBto Cの話題になりましたが、B to Bの動きについては連載後半で取り上げる予定です。
|