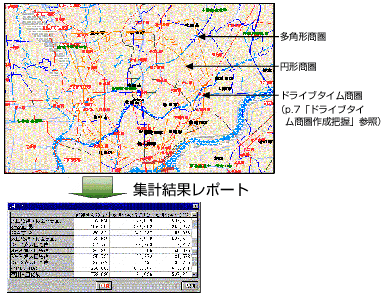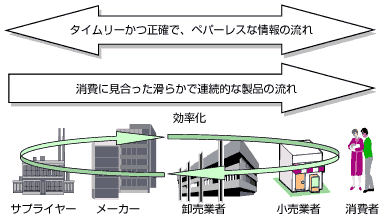商圏把握による経営戦略 小売店は店舗を構えて来店する消費者の日常的な購買によって販売活動が支えられています。新規出店に際して最も重視されるのが立地条件でしょう。駅前の商店街であるのか、幹線道路沿いであるのかによって、商圏の捉え方が大きく異なります。また店舗規模の大小も消費者の吸引力を決める大きな要素です。
一般に「商圏」とは、店舗が顧客を吸引できる地理的な範囲を指します。(表1)は最寄品、買回品の商品特性別に距離と人口で商圏を定義した一例です。
実際の商圏把握では、地域特性や競合状況等の条件を考慮することが必要ですので、さらに詳細な検討を行うことになります。有名な商圏把握法にアメリカの経済学者デービッド・ハフ氏による「ハフモデル」と呼ばれるものがあります。それを通産省が日本型にアレンジした「修正ハフモデル」が普及していますが、その考え方は、「ある地域に住む消費者が、ある商業集積で購入する確率は、商業集積の規模に比例し、そこに到達する時間距離の2乗に反比例する」というものです。つまり面積に比例し、距離の2乗に反比例するというわけです。この考え方を用いて競合店との小売吸引率計算を行うことができます。
| 表1 |
|
最寄品の商圏
| 業種・業態 |
商圏距離 |
商圏人口 |
| 鮮魚店、青果店 |
〜500m |
3,000人 |
| 薬局・薬店 |
500m〜1km |
1万人以上 |
| ミニ・スパー(150坪以内) |
500m〜1km |
1,500世帯
(4,500人) |
| CVS(都市型) |
〜500m |
1,000世帯
(3,000人) |
| ドラッグストア |
〜1km |
2万人以上 |
|
|
|
|
|
買回品の商圏
| 業種・業態 |
商圏距離 |
商圏人口 |
眼鏡店(市街地型)
(郊外型) |
2km
5〜10km |
2万人
10万人 |
| 靴店、玩具店(郊外型) |
5〜10km |
5万〜10万人 |
書店(市街地型)
(郊外型) |
1〜2km
3〜5km |
3万人
5〜10万人 |
| 紳士服店(郊外型) |
10〜15km |
20万人 |
| スポーツ用品店(郊外・総合店) |
10〜15km |
30万人 |
GMS(市街地)
(郊外型) |
10km
10〜20km |
7万〜10万人
10万〜15万人 |
| DS(ディスカウントストア) |
10km |
20万人 |
| 百貨店 |
50〜80km |
30万人〜 |
|
|
| 出典:「すぐできる商圏と売上高予測」(市原実著、同友館) |
|
GISによる商圏把握 商圏把握をコンピュータの画面上で行うことができるのが、GIS(Geographic InfomationSystem,地理情報システム)と呼ばれるシステムです。GISは、〔1〕地図を表示する地図ソフト、〔2〕商業施設のポイントデータ、地図データ、統計データなどの「データベース」、〔3〕統計解析ソフトで構成され、各種データを一枚の地図上に重ね合わせて地理情報を視覚的に表現させることができます。主に、出店計画等のマーケティング戦略に活用されていますが、競合対策等の経営戦略を見直すのに有効な点では既存店にも活用できるシステムです。
このGISでは、ある地点から半径距離を指定した円形商圏内を描き、その商圏に含まれる統計情報を自動集計したり、商業施設等のポイントデータを一覧表示したりすることができます。また前述のハフモデルでは商圏吸引率を計算する機能も備えています。
小売業のエリアマーケティングをサポートする強力なツールといえますが、難点は価格がまだまだ高いことです。そのため個店レベルで導入するには難しいシステムですが、(財)滋賀県産業支援プラザでは、小売業者へのサービスとして「商圏マップ」による各種商圏情報の出力を行っていますので活用するとよいでしょう。
仕入先との共同戦略−SCM 店舗運営をする上で一個店レベルの取り組みを超えて、メーカー、卸売と共同で消費者ニーズの動向に合わせてジャスト・イン・タイムで商品供給のフローを効率化させようとする取り組みが注目されています。これはサプライチェーン・マネジメント(SCM)とよばれる経営管理手法です。
従来の商取引においては、小売、卸売、メーカー間において、それぞれの判断によるリスク負担で受発注業務が行われてきました。そのため、最終消費者の需要動向に対する予測がまちまちで、中間流通における商品在庫が偏在して過不足を生み、販売の機会損失、不良在庫等を招いています。そうした商品供給(サプライチェーン)の業務プロセスを統合的な視点から一つのビジネスプロセス・システムとしてとらえなおし、企業の壁を越えて全体の最適化をめざそうという発想がSCMの基本です。
このSCMの考えは、繊維・衣料品業界のQR(QuickResponse)や食品・日用品業界のECR(Efficient ConsumerResponse)という取り組みの流れを受け継いでいます。さらに遡れば元もとの原型は、最終工程から前工程へ生産指示を出していくトヨタのカンバン方式(JustinTime)にあります。
アメリカにおけるQRの事例では、売上や商品回転率の増加、在庫削減においてめざましい成果が報告されています。ECRの例では、P&Gとウォルマートの取り組みが有名ですが、日本においても、ジャスコや、平和堂(滋賀県)、ラピタ(島根県)などの地方スーパー等でも先進的なシステムが構築されています。
SCMの経営管理手法を実現するためには、情報技術の活用が不可欠です。小売のPOSデータを卸売、メーカーとリアルタイムに共有できる情報ネットワークの仕組みやペーパーレスな受発注業務の仕組み、需要予測システム、迅速で継続的な在庫補充の体制等が必要になってきます。
| 図2 SCM(サプライチェーンマネジメント) |
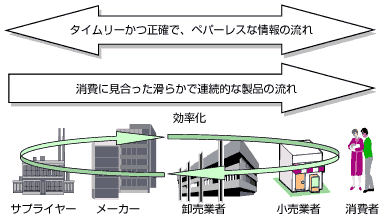 |
中小小売店のSCM戦略 こうしたSCMの仕組みを支える情報システムは大手企業が中心になって構築されています。しかし中小規模の小売店においても、例えば多店舗展開を計画して効率的な受発注システムや在庫管理システム等を構築しようとすれば、このような仕入先との連携でサプライチェーン全体の最適化を考えることは重要です。
具体的には、〔1〕JANコード(バーコード)による単品管理とPOSシステム、〔2〕情報ネットワークによる発注、仕入業務の合理化、ペーパーレス化、〔3〕迅速な商品供給と多頻度小口配送、〔4〕定番商品の連続的自動在庫補充方式(CRP)というようなシステム導入が可能かどうかが検討テーマになります。
現実には旧来の商取引慣習が障壁となったり、大手取引先との力関係で計画通りに進まないことも多いと思われます。例えば、衣料品業界のQRは、日本では依然としてJANコードの普及率が低く、相変わらず小売店での独自商品コードでラベル付けが行われています。また、大手スーパー等にテナントとして入っている小売店では、POSシステムでJANコードによる売上登録をすると直営部門と識別できないとの理由で、わざわざ別の商品コードを付けたりしています。積極的な小売店は、自前のPOSを持ちこんで単品管理しているのが現状です。
しかしそれでもやはりサプライチェーン全体の視点で、流通全体の効率化とコストダウンを図る努力は必要です。戦略的な思考と工夫で次の時代のあるべき姿を眺望したいものです。
|