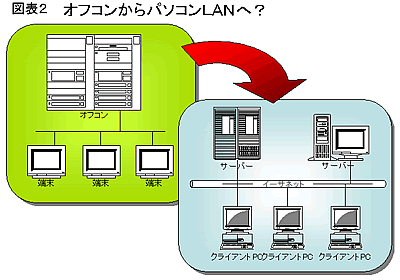第6回オフコンとパソコンLAN
若松経営情報研究所
中小企業診断士・システムアナリスト 若松敏幸 |
| ●オフコンのリプレース(入れ替え)をどう考えるか |
| オフィス用のコンピュータ、略してオフコンは、日本では80年代から市場に普及し、今日も相当数の企業において利用されています。90年代半ばからのダウンサイジング(低価格で高機能な小型コンピュータの登場)の動きに押されて、オフコンの普及率は低下していますが、それでも基幹系システムとしてまだまだ活躍しています。20世紀末の「コンピュータ2000年問題」を機に、オフコンからパソコンLANへ切り替えた企業も多いようですが、IT(情報技術)のトレンドに合わせてどの企業でもすぐに切り替えることができるものではありません。今回は、このオフコンのリプレース(入れ替え)の問題について考えてみます。 |
N社は、賃貸の不動産仲介業を営む中小企業です。8年前に導入したオフコンが、メーカーの部品供給保証期間が切れる時期にあたりますので、保守の問題からそろそろ次のハードウェアに切り替えようと考えています。情報システム室のO主任は、次期システムのモデルとして、従来のオフコンの上位機種へリプレースするという方法で検討しました。この方法ですと、これまでのプログラム資産やデータの移行が容易ですので、短期間で新システムを構築することができます。 しかし、N社のP社長は、「せっかく新しいシステムにするなら、これまでのシステムをそのまま乗せるのではなく、システムの機能を見直してパソコンLANで再構築したほうがよくはないか」という考えを持っています。O主任は必ずしもオフコンにこだわっているわけではありませんが、新システム構築の期間やパソコンのシステムの安定性などに対する不安から、安全策をとるほうが望ましいのではと思っており、P社長の考えに賛同しかねています。 取り引きのあるコンピュータ・ディーラーから提案されているのは、オフコンの上位機種へのリプレースです。また、別のソフトハウスから提案されているのは、パソコンLANのクライアント・サーバー・システムです。新型オフコンへのリプレースのほうが費用が安く、導入期間も短いのでメリットが大きいのですが、P社長の考えも一理あると思うので、最終案をどうするか思案にくれているところです。 |
| ●メーカー独自仕様のオフコンと、オープン環境のパソコン |
前回、K社の事例を紹介しましたが、それはオフコンからパソコンへ切り替えるという前提でパッケージソフトの選定方法を検討するというテーマでした。しかし、その前提以前に、旧オフコンを最新のオフコンへグレード・アップするという選択肢もあったはずです。今回のN社ののように、従来のプログラム資産を容易に捨て去ることができないという場合は、最新機種のオフコンへリプレースするという選択肢も検討する必要があります。 オフコンか、パソコンLANかの問題は、つまるところ、メーカー独自仕様のクローズドなシステムか、デファクトスタンダード(事実上の標準)に準拠したオープンなシステムかの問題です。 前者は長年の実績で運用面での安定性や信頼性が高く、メーカーのサポートも充実しています。一方、後者は、競争原理の働くオープン環境であるためハード、ソフトが低価格化・高機能化し、将来的な機能拡張も容易であるというメリットがあります。デメリットとしては、前者の場合は特定メーカーのハード、ソフトに依存するため費用が高くつき、後者の場合は、製品の選択やトラブル時の対応において複数のベンダーと交渉を行うなど、ユーザー自身の問題解決能力が必要になってくるという点です。 |
| ●オフコンかパソコンかの選択基準を整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N社のように、長年開発してきたプログラムが豊富にある場合は、ITの時流がパソコンにあるからといって、おいそれとオフコンを捨て去り、すべてをパソコンLANに切り替えることは難しいでしょう。O主任が躊躇したのは、パソコンで従来のオフコンのアプリケーションと同様のものを構築しようとすると、プログラム開発の期間や安定稼動までの日程が長くかかることや、費用もけっして安く済まないと思われたからです。ところがオフコンを新機種に切り替えるだけなら、ハードの費用は高くつくもののプログラム資産はそのまま生かせるので全体としては導入コストは割安になります。また、ユーザーのオペレーションを変更しなくても済みます。 図表1は、O主任が両者の特徴を比較して整理したものです。この図表は、N社の状況を前提にしたものですので一般的なものではありませんが、オフコンとパソコンLANを比較検討する際の参考になるでしょう。 図表1 オフコンとパソコンの比較(N社の場合)
|
| ●企業の実情にあった機種選定と円滑な移行計画を |
もし従来のプログラム資産がそれほど大きなものでない場合や、全面的にスクラップして再構築すべき状況にある場合、あるいは、新規のシステム導入である場合などは、それほど迷うことなくパソコンLANのクライアント・サーバー・システムを選択できるものと思われます。 多くの場合、「オフコンかパソコンか」で問題となるのは、長年オフコンを利用してきた中堅企業の場合でしょう。「短期的には、上位機種のオフコンのほうが安く、速くシステム導入できる。しかし、中長期的には、オープン環境のパソコンLANを導入するほうがコスト面や機能面でメリットが大きい。」そのように判断される場合、どちらを選択すればよいのでしょうか? 企業環境の変化があまり急でなく、企業活動や組織を大きく変更させる必要がない場合は、安定した従来のオフコン・システムを維持しながら、必要に応じて新機能を追加導入するという考えでよいでしょう。オフコン・メーカー各社は、パソコン連携機能やWEB対応などのための方法論やツール類をいろいろ提案しています。改めてパソコンLANに全面的に移行する必要性は少ないものと思われます。 しかし、環境変化が大きく、競争の激しい企業においては、情報システム自体も柔軟性に富み、最新の機能を装備していることが要求されます。そういう場合は、段階的にオフコンからパソコンLANのシステムへ移行する計画を立てることも一つの解決策です。 例えば、最初の段階では、オフコンの機能を現状維持に留めて(オフコンを上位機種にリプレースはするがプログラムは従来どおり)基幹系システムで利用し、一方で情報系システムにパソコンLANを新たに導入して、オフコンとの連携機能を持たせるという方法が考えられます。オフコンのデータをパソコンLAN側からアクセスして、データ加工・分析できる仕組みです。ここで基幹系システムとは、販売・購買・生産・会計などの基幹業務を効率化する目的のシステムのことを指し、情報系システムとは、データを加工・分析して意思決定を支援するためのシステムのことを指します。そして第2段階として、やがて部分的な保守ではなく全面的な機能刷新の時期が来たら、パソコンLANへ全面的に切り替えるという方法です。その場合は、既存のオフコンのプログラム資産を廃棄することを意味します。 メーカーによっては、パソコンのOS上でオフコンのプログラムが稼動する方法を提供している機種もありますが、プログラムのスクラップ&ビルド(廃棄と再構築)についての考え方は上記の方法と同じです。 企業の情報システムは、経営戦略と中長期の経営計画を実現させるために構築されるものです。初期導入費用だけでなく、運用・保守などの様々な費用もトータルに考えた上で、上記図表1にあげたような項目で費用対効果の高い方法を選択すべきでしょう。必ずしも最新のITがすべての企業に有効とは限りませんので、その必要性に応じて最適なシステム構築方法を選択することが望ましいといえます。オフコンとパソコンLANの選択の問題も、そういう視点で捉えることが必要でしょう。
|