第8回情報リテラシーの向上策
若松経営情報研究所
中小企業診断士・システムアナリスト 若松敏幸 |
| ●中小企業から寄せられる情報化に関する相談 | |
| 中小企業の情報化を左右する問題の一つが、社員の情報活用能力の問題です。今回は、この問題について取り上げてみたいと思います。次のような事例で考えてみましょう。 | |
|
| ●情報リテラシとは何か |
P社の場合の問題点は、まず社長を含む管理職の情報リテラシの低さにあります。それがP社の情報化を遅らせている大きな原因でしょう。コンピュータを単なる事務処理の効率化を図る道具として捉えているのでは、競争の厳しい今日、ライバルに大きく差をつけられてしまいます。 ここで、情報リテラシとは何かを定義しておきましょう。 |
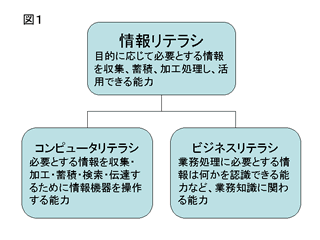 |
P社の場合は、コンピュータリテラシとビジネスリテラシの両面で問題がありそうです。 コンピュータは販売管理、財務管理などに使われていますが、取引先とのコミュニケーションが重要な営業部門に一人一台のパソコンが整備されていません。また、事業活動について目標と実績を計数的に管理すべき管理職にも全員にパソコンの環境はほしいところです。こうした環境整備の上に、キーボード操作などの初歩的な能力を早急に身につけさせる必要があります。 一方、ビジネスリテラシはビジネスにコンピュータを活用する能力にあたりますが、これは社員個人レベルの能力訓練だけで解決する問題ではありません。ワープロや表計算ソフトで文書を作成する能力の上に、必要に応じた情報の収集と選択、そして編集加工という高いレベルの業務能力が必要であり、そのための仕事の進め方に関する社内ルールの変革も不可欠だからです。例えば、従来の紙ベースの仕事の仕方から脱皮してペーパレス化を進めようとすれば、情報共有の仕組みや報告・連絡・相談・決裁などの業務ルールを変更せざるを得ないでしょう。 |
| ●情報リテラシの向上策 |
それでは具体的に、社内の情報リテラシを向上させるにはどのような取り組み方をすればよいでしょうか。 |
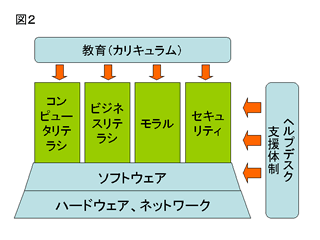 |
情報リテラシ向上策の第1段階は、今後の社内情報化のビジョンと目的の明確化が前提になります。社員の情報リテラシはどうあるべきか、そのための情報システムのインフラ(ハード、ソフト、データベース、ネットワーク等)はどこまで整備する必要があるのかを計画します。この段階では、販売管理、生産管理などの「基幹系システム」とは別に、非定型的な情報を扱う意思決定支援のためのシステム、すなわち「情報系システム」の構築がテーマになりますので、自社のレベルに合ったイントラネットなどを検討することになるでしょう。 実はこの段階が一番やっかいで、なかなかパソコン操作に慣れない「キーボードアレルギー」の中高年社員が多いものです。パソコンを使って仕事をすることで効率が上がり、達成感も得られるように、まずは簡単なレポート作成などから始めるのが順当でしょう。また、困ったときにはすぐに人に聞けるように、部署内に一人はサポート要員を任命して支援させる体制も作っておきたいものです。情報システム室などの部署があれば、全社的なヘルプデスクの支援体制も整える必要があります。 自発的な能力向上を待つだけではなかなか全体の能力は向上しませんので、思い切って会議でのレポートはすべてパソコンで作成することなどを義務付けることも必要になるでしょう。 第3段階は、インターネットなどの外部情報の収集能力や、社内の共有データベースの情報活用の能力を高めることを目指します。収集した情報を自分に合うように加工するための技術も磨いていく必要があり、表計算ソフトの高度な機能や、プレゼンテーションソフトなどの効果的な使い方なども習得することが目標になるでしょう。 電子メールで社内外の人とコミュニケーションができるようにすることもこの段階では不可欠なテーマになりますが、単にメールの送受信の技術だけではなく、メール交換の基本的なマナーやモラルなどもしっかり身につける必要があります。また、昨今、コンピュータ・ウイルスなどが猛威を振るっているだけに、セキュリティ対策の知識も必要です。 |
| ●社内業務のルール、組織、評価制度の見直し | ||||||||||
冒頭のP社の社長は、情報化に対して消極的でしたが、経営トップの意識が低ければ社内の情報リテラシは向上しません。社員がどんなにパソコンを上手に使いこなせるようになっても、その能力を評価し、活用する仕組みが会社の中に存在しなければ、経営者には単なる「お遊び」にしか映らないからです。 情報リテラシ向上策の第1段階で、情報化ビジョンが前提になると述べましたが、そのことは会社の情報化戦略なしでは進まないことを意味します。経営トップのリーダーシップが不可欠な要素になるのです。また、社内の業務のあり方を見直し、スピーディに意思決定が出来るような情報収集と交換の仕組みや組織をどのように構築するのかを考える必要もあるでしょう。大きな規模の会社では、ピラミッド型の管理階層からフラットな組織へと変革が進んでいるように、情報化は組織変革にも大きな影響を及ぼします。 煩雑な手続きを電子的に簡素化することで、主体的に決断する機会も増えてくるでしょう。社員の創造的な活動を促進させることで、組織全体の機動力を高め、ひいては競争力を強化することにもつながります。そうした活動に結びつく情報を積極的に提供する社員を褒賞したり、評価基準に反映させるなどの啓発的な人事制度を導入することも検討に値します。 情報リテラシの向上は、組織全体の能力を高めるばかりか、感情のこもった情報交換が行きかうことで人間関係にふくらみをもたらせてくれます。豊かな組織文化を作り出す上でも、今日の企業経営に不可欠な要素だということが出来るでしょう。
|
||||||||||