第10回システム導入前に行う運用準備
若松経営情報研究所
中小企業診断士・システムアナリスト 若松敏幸 |
| ●システム導入を間近にして | |
| 企業の情報システムを構築する場合、そのシステム開発の作業が終盤にさしかかると、ユーザー企業側では導入準備に入る必要があります。その際にユーザー企業側で取り組むべきことについて考えてみたいと思います。次の事例をご覧下さい。 | |
|
| ●システム導入前の準備 |
情報システムを構築するのは、建物を建てるのに似ているかもしれません。どんな家を建てるのかという目的とコンセプトを明確にし、予算の許す限り住みやすさを最大限に追求しようとするのは、まさにシステム開発の作業と類似しています。建物が完成間近になると、施主は入居のための準備に入ります。どの部屋を誰に割り当て、どのような家具を置くのか、入居の日程はいつにするのか、など。家具の配置は単にスペースの問題ではなく、そこに居住する者にとっていかに使いやすいかという機能性を考えてレイアウトを考えることでしょう。 情報システムの場合も、それと同じことが言えます。システムの中にデータを入力したり、出力したりするのは日常業務のことですから、使いやすさへの配慮は大事なことです。しかも毎日の業務は必ず何か変則的な出来事が発生しますので、そうした場合にどう対処すればよいのかということも十分に考えておく必要があります。 上記のS社の場合は、あらかじめ導入前の準備として、次のようなことを考えていました。 会計や給与計算などの他の部門と独立した業務の場合であれば、このような準備で事足りるでしょうが、組織形態によってさまざまに異なる業務(販売、仕入、生産などの業務)の場合、これだけでは不十分です。 |
| ●「操作マニュアル」の完成度 |
ベンダー(システム供給業者)とのシステム開発の請負契約書において、納入される成果物として、プログラムのほかに設計書や操作マニュアルなどのドキュメント(文書)も明記されるのが普通です。その納入成果物であまり問題視されることが少ないのが「操作マニュアル」です。 「操作マニュアル」とは何かというと、会計ソフトなどのパッケージに何冊も同梱されているものを思い浮かべると良いでしょう。一般にパッケージソフトのマニュアルは、懇切丁寧に記述されているものが多く、初心者にはその全部に目を通すことはなかなか骨の折れる作業です。 しかし、パッケージソフトではなく、ユーザーのニーズにあったカスタム・メイドのシステム開発を行った場合、ベンダーが作成する「操作マニュアル」は簡単なものが多く、単に各画面のボタン操作を説明したレベルのものがよく見受けられます。システムの設計段階などでは、ベンダーはユーザーと何度も会議を重ねて、システムの機能について詳細に検討しますが、この最後の納品物である「操作マニュアル」については、あまりその完成度はチェックされることはありません。 マニュアル作成に多くの費用をかけられないという事情もあって、ユーザーも「トラブル発生時の対応さえしっかりしてくれれば、マニュアルは簡単なものでよい」と、目をつむっているのが現状です。しかし、できればシステム機能上の制約事項や、どの業務はどの手順で処理をすればよいのか、またエラー発生時などの対応はどうすればよいのか等もていねいに記載してほしいものです。S社の場合もまさにこのことが言えるでしょう。 |
| ●「業務運用マニュアル」を作る | ||||||||||||
マニュアルには、もう一つ「運用マニュアル」と呼ばれるものがあります。通常、コンピュータのハードや基本OS、アプリケーション・プログラム等の運用・保守業務の際に作成されるものを指しますが、それとは異なり、ユーザーの立場で業務の流れに即したシステム運用の「業務運用マニュアル」が是非とも欲しいものです。どの部署の、誰が、いつ、どのような手順でコンピュータの運用を行うのか、というマニュアルです。これはベンダーに作ってもらうのではなく、ユーザー側が自分自身で作成することが望ましいといえます。 表1は、その運用マニュアルの作成方法ポイントをまとめたものです。また表2は、ある業務処理の流れを一枚のシートに作成した簡易版の運用マニュアルのサンプルです。 |
||||||||||||
| 表1 運用マニュアルの作成方法
|
||||||||||||
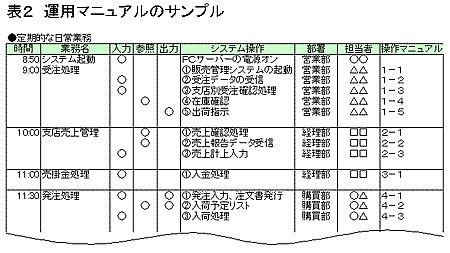 |
||||||||||||
その作成は決して難しいものではありませんので、システム導入前の準備として、システム全体を改めて把握するつもりで作成すると良いでしょう。このマニュアルによって、コンピュータの操作担当者も、自分がどの処理を受け持つべきか、そしてその処理がいつ、誰に引き継がれるものかが分かり、操作上の不安感を取り除くことができます。 この運用マニュアルは、最初から高い完成度を目指す必要はありません。日々の業務の中で、操作担当者から上がってくる質問や問題発生への対処のたびに、徐々に詳細化して利用しやすいものに作り上げていけば良いでしょう。 マニュアルの完成度を上げていく秘訣は(運用マニュアルと操作マニュアルに共通して言えることですが)、日々発生するトラブルについて、「トラブルの症状、原因、対策、今後の課題」という項目に分けて詳細に記録をとっていき、トラブル記録の一覧を作成することです。こうすることで、どんな問題が頻繁に起きるのか、どの問題が解決済みで、どれが未解決なのかということが把握できます。対応策として運用上の処置で解決するものであれば、それを運用マニュアルに盛り込めばよいのです。こうして自社独自のマニュアルが出来上がっていきます。それは同時に、導入されたシステムの品質管理にもつながります。 情報システムは、プログラムが完成してユーザーに引き渡された時点で、ユーザーの所有物です。その運営、管理の方法はユーザー自身が工夫をして使いやすいものに育てていくという考え方が必要です。ユーザー自身のIT活用・管理能力を高めていくことが、コンピュータ導入の成功の鍵を握っています。 |